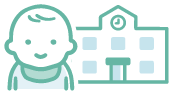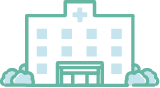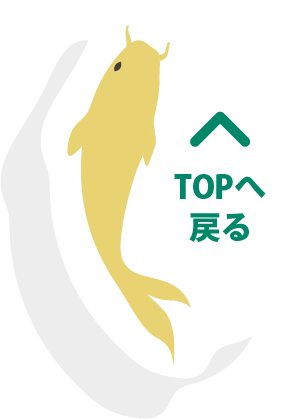本文
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
小千谷市内にある相続により発生した空き家について、本制度の適用を受けるために税務署への提出が必要な書類の一つである「被相続人居住用家屋等確認申請書」の交付を行います。
制度の概要
被相続人の居住の用に供していた空き家を相続した相続人が、耐震リフォーム(耐震性のある場合は不要)または家屋取壊し後に、その家屋または敷地を譲渡した場合には、その譲渡所得から3,000万円を特別控除することができます。
特例を受けるためには、空き家所在地の市町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたうえで、税務署にて確定申告を行う必要があります。
特例措置に関する詳細は、次のホームページをご覧ください。
令和6年(2024年)1月1日以後に行う譲渡について(令和5年度税制改正)
令和6年(2024年)1月1日以後に行う譲渡については、以下の変更点があります。
- 当該家屋の買主が、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、全部を取り壊した場合又は耐震リフォームにより耐震基準に適合する工事をした場合も、本特例措置が適用されることとなります。
- 被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合の特別控除額は、2,000万円となります。
制度の適用要件
- 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡で、特例の適用期限である令和9年(2027年)12月31日までに譲渡すること。
- 被相続人が相続直前まで当該家屋に居住していたこと。
- 相続の直前において、被相続人以外の居住者がいなかったこと。
- 相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付けの用、または居住の用に供されていなかったこと。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。
- 譲渡価額が1億円以下であること。
- 家屋付きで譲渡する場合、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。
※一定の条件を満たせば、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も制度の対象となる場合があります(2019年4月1日以降の譲渡のみ)。
※制度の詳細や要件については国土交通省および国税庁のホームページをご確認いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。
「被相続人居住用家屋等確認確認書」の交付の流れ、必要書類について
下記の被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式第1号)(以下、申請書)に必要事項をご記入のうえ、添付書類を添えて市にご提出ください。申請書は、譲渡の内容や譲渡した年によって異なります。譲渡内容にあったものを下記様式からお選びください。
添付書類は、譲渡の内容や個々の事情により異なります。詳細は、申請書の「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」や下記の「記載例及び添付書類の入手方法について」をご確認ください。
被相続人居住用家屋等確認申請書の様式
令和5年(2023年)12月31日までに譲渡した場合
- 別記様式1-1(耐震基準を満たしてから譲渡した場合) [Wordファイル/84KB]
- 別記様式1-1(耐震基準を満たしてから譲渡した場合) [PDFファイル/231KB]
- 別記様式1-2(取り壊してから譲渡した場合) [Wordファイル/90KB]
- 別記様式1-2(取り壊してから譲渡した場合) [PDFファイル/248KB]
令和6年(2024年)1月1日から令和9年(2027年)12月31日までに譲渡した場合
- 別記様式1-1(耐震基準を満たしてから譲渡した場合) [Wordファイル/88KB]
- 別記様式1-1(耐震基準を満たしてから譲渡した場合) (PDF 219.0KB)
- 別記様式1-2(取り壊してから譲渡した場合) [Wordファイル/94KB]
- 別記様式1-2(取り壊してから譲渡した場合) [PDFファイル/253KB]
- 別記様式1-3(譲渡してから耐震改修または取り壊した場合) [Wordファイル/97KB]
- 別記様式1-3(譲渡してから耐震改修または取り壊した場合) [PDFファイル/261KB]
※耐震基準適合証明書 [Wordファイル/92KB]/耐震基準適合証明書 [PDFファイル/139KB]
記載例及び添付書類の入手方法について
提出先
〒947-8501 新潟県小千谷市城内2丁目7番5号
新潟県小千谷市防災安全課
電話 0258-83-3515
留意事項等
- 「被相続人居住用家屋等確認申請書」の発行手数料は無料です。
- 申請書(別記様式第1号)は、上記リンクまたは国土交通省ホームページなどからダウンロードください。(全国統一の様式です)。
- 相続人が複数人(共有名義)の場合は、相続人ごとに申請書を作成してください。
- 交付まで2週間程度かかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等に日数を要することがありますので、税務署への手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
- 郵送での交付をご希望の場合は、申請書と必要書類に加えて、返信用封筒(送付先の住所・氏名を記載の上、返信分の切手を貼ったもの)を同封してください。
- 「被相続人居住用家屋等確認書」は、確定申告の際に税務署へ提出する書類の一つであり、本市より確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けられない場合があります。本特例の適用の可否等については、事前に管轄の税務署へお問い合わせください。
よくあるご質問
全般
相続人である2人が譲渡所得を得た。誰が手続きをしたらよいか。
特例措置を受けようとする相続人ごとに手続き(確認書の取得・確定申告)が必要です。
「譲渡日」にはどの日付を記載したらよいか。
売買契約の締結日又は所有権の移転日(引渡し日)のいずれかを記載してください。
ただし、家屋取壊し後の敷地を譲渡する場合(様式1-2)に譲渡日を売買契約の締結日とするときには、売買契約締結時までに家屋の取壊し等が完了している必要があります。
老人ホーム等の施設ではなく、介護のため子の家に移り、そこで亡くなった場合はこの特例を受けることはできるか。
親族の家や一般の賃貸住宅に転居して亡くなった場合は、この特例を受けることはできません。
閉鎖事項証明書の代わりに登記完了証の提出でよいか。
登記完了証は、被相続人居住用家屋の取壊し(滅失)日が確認できないため、閉鎖事項証明書(建物)が必要となります。
様式1-2(家屋取壊し後の敷地を譲渡する場合)
添付書類である写真に日付を追加する場合、元の写真を加工して日付を入れたものでよいか。
写真への日付の追加については、データを加工して追加しても、手書きでも構いません。
建物が未登記であったたため、添付書類である閉鎖事項証明書(法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書)がない。代替書類は必要か。
必要です。除却工事に係る請負契約書のコピーなど(請求書、領収書)を提出してください。
様式1-3(買主が譲渡後に耐震リフォーム又は取壊しする場合)
譲渡後、買主の都合で期日までに取壊し工事が完了しなかった。この場合確認書の発行は可能か。
譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに工事を完了することが必要です。これを過ぎた場合、確認書は発行できません。
買主が譲渡後に工事を行うため、売主が買主から必要書類を受け取ることもあると思うが、どのようにすればよいか。
基本的には買主から売主へ交付してもらいます。そのため確実に買主から書類を交付してもらうため、契約時に特約等で取り決めることが重要です。